| 1,総則 | |||||||||||||||
| 1-1 | FJはワンデザイン級である。 本規則の意図するところは艇が艇型、艇体重量、センターボードおよび舵板の形状、マストとその重量、セールプランにおいて出来る限り同じようになることを確保するにある。 |
||||||||||||||
| 1-2 | 本クラスの公式の言語は英語であり、解釈上の問題点については英文規則書が優先するにある。 | ||||||||||||||
| 1-3 | 本規則は、図面、計測定規、計測図と相互に補完する。 解釈はすべてISAFが行うが国際FJ協会(IFJO)と協議することが出来る。 |
||||||||||||||
| 1-4 | 本規則、計測定規や図面間の相違点についてはISAFに照会するものとする。 | ||||||||||||||
| 1-5 | その国に管轄当局がないか、或はその当局が本クラスの管轄をしない国においては、本規則上指定された機能はIFJOのような代表として委任されたもの(国内協会)が行う。 | ||||||||||||||
| 1-6 | ISAFやIFJOは本規則や図面或は之等から生じる紛争に関してはいかなる法律上の責任も引き受けない。 | ||||||||||||||
| 2,建造者 | |||||||||||||||
| FJはどのような造船所でも、素人の手で作ってもよく、建造上の許可証も必要ない。 | |||||||||||||||
| 3,国際クラスフィー | |||||||||||||||
| 3-1 | 国際クラスフィーの額は毎年IFJOと協議しISAFにより再検討される。 | ||||||||||||||
| 3-2 | 国際クラスフィーの徴収と配分の責任はISAFにある。 | ||||||||||||||
| 3-3 | 国際クラスフィーの最終的に計測と登録が行われると否に拘らず、各艇毎に造船者が支払うものとする。国際クラスフィーは1992年現在39、4英ポンドである。(日本FJ協会では、登録計測料と共に40、000円とする。)支払いはISAFに対し行い、ISAFは国際クラスフィー領収書と銘板を渡すものとする。国際クラスフィーの銘板は造船所が艇体に取り付け、領収書は艇のオーナーに渡される。 | ||||||||||||||
| 3-4 | 1974年7月1日以前に計測登録された艇は国際クラスフィーの銘板は必要としない。 | ||||||||||||||
| 4,登録 | |||||||||||||||
| 4-1 | 有効な計測証明書と国際クラスフィーの銘板のない艇は本クラスのレースに参加することは許されない。(規則3-4参照) | ||||||||||||||
| 4-2 | 日本FJ協会はセール番号を発行し、そのセール番号は一連のもので、且つ、国際競技に出場する艇はその番号の前に国際文字(JPN,1993年4月1日前計測分はJ)を付けるものとする。 日本FJ協会は国際クラスフィーを受け取った後、セール番号を発行するものとする。 |
||||||||||||||
| 4-3 | 同一国内で登録された艇で、同一船名のものが2隻あってはならない。 | ||||||||||||||
| 4-4 | 証明書の取得は次の通りとする。(本項は日本FJ協会の特別規定)原規則は括弧内に示す。 | ||||||||||||||
| (Ⅰ) | 日本FJ協会は多数艇分を一括して国際クラスフィーをISAFに支払う。オーナー又は造船所から国際クラスフィーの支払いがあったとき日本FJ協会はセール番号を発行する。 | ||||||||||||||
| (Ⅱ) | オーナー又は造船所は当協会の公式計測員によりその艇の計測を受けなければならない。公式計測員は本規則により記入した計測所3部を作成し、その1部はオーナー又は造船所に対し計測証明書として発行する。1部は日本FJ協会に発送し、1部は公式計測員の控とする。造船所は艇を計測証明書と共にオーナーに引き渡さなければならない。 | ||||||||||||||
| 原規則(Ⅰ) | オーナー又は造船所は国際クラスフィー領収書を同封し、同時に希望する船名を申し出てセール番号の交付を該当協会に申請するものとする。該当FJ協会は国際クラスフィー領収書にセール番号を記入する。 | ||||||||||||||
| (Ⅱ) | オーナー又は造船所は当協会の公式計測員によりその計測を受けなければならない。本規則により記入された計測所3部が艇のオーナーに与えられる。 | ||||||||||||||
| (Ⅲ) | オーナーは記入済みの計測所3部を登録料と共に該当協会に送付しなければならない。これを受け取り次第該当協会はオーナーに計測証明書を発行する。本証明書は計測書に記入された事項を含むものである。 | ||||||||||||||
| 4-5 | 所有権が移転した場合、証明書は無効となるが再計測は必要としない。新オーナーはこの際旧証明書を返却すると共に必要事項を記入して、当協会へ新証明書の交付を申請することが出来る(登録変更手数料は不要。)新計測証明書か訂正した原計測証明書がオーナーに交付される。 | ||||||||||||||
| 4-6 | オーナー所有の艇体・スパー類・セール・艤装品を常にクラス規則に合致させ、且つ、艇・スパー類・セール或は艤装品を改造復旧や修理により常に計測証明書を無効にしないようにするのはオーナーの責任である。 | ||||||||||||||
| 4-7 | これらの規則に包含されている事項の如何に拘らず、ISAF又は当協会は、どの艇に対しても計測証明書の発行を拒否又は回収する権限を有する。 | ||||||||||||||
| 4-8 | ISAFは定期的に各国FJ協会からセール番号、発行済み計測証明書の明細と共にオーナーの氏名、住所及び計測書又は計測証明書のコピーを報告を求めるものとする。 | ||||||||||||||
| 5,計測 | |||||||||||||||
| 5-1 | 本協会の公式計測員のみが、艇、スパー・セール・艤装品を計測し、本規則に合致しているという判定署名を計測書に記入するものとする。 | ||||||||||||||
| 5-2 | 計測許容公差は正当な建造上の誤差のみを許すためのものであって、デザインを故意に変更するために使用されてはならない。 異常であるとか、艇の本来の性格から逸脱するとか、本クラスの全体の利益に反するとか見做されるものをすべて計測員は計測書により報告しなければならない。この場合、本規則の明確な要求事項を満たしていても計測書が発行されないことがある。 |
||||||||||||||
| 5-3 | 計測員は自己の所有、又は自身の建造したもの、或は利害関係を有している艇・セール・スパー・艤装品の計測は出来ない。 | ||||||||||||||
| 5-4 | 新調又は重大な改造を加えたセールは公式計測員のより計測され、計測員はセールのタック、スピンネッカーではトップの近くにスタンプ又はサインをし日付を記入しなければならない。 | ||||||||||||||
| 5-5 | 公式計測に使用するテンプレートはISAFより供給されるものとする。 テンプレートはヒンジなしの全幅か、固定できるようになった半幅の折り畳みのものとする。 半幅のテンプレートを使用し上述のテンプレートで計測されてない、1980年4月1日前のモールドで建造され、且つ、1982年4月1日前に計測された艇は、将来もすべてのレースに権利を有する。 |
||||||||||||||
| 5-6 | すべての艇・スパー・セール及び艤装品は現行規則又は計測書が発行された時点での該当規則の何れかに適合しなければならない。どのような改造、復旧でも現行規則に合致するべきである。 | ||||||||||||||
| 5-7 | すべての艇体・スパー類・セール及び艤装品は、本協会又はレース委員会の裁量による再計測を受けなければならない。 | ||||||||||||||
| 6,認識マーク | |||||||||||||||
| 6-1 | 艇体は刻印又は消えない印の何れかでセンターケースの背又は頂部に、又はシュラウド金物の近くに高さ25mm以上の文字でセール番号と国籍文字を付けなければならない。艇が他国に売却されたときは前のマークに付け加えて新しいセール番号と国籍文字を付けなければならない。 | ||||||||||||||
| 6-2 | 艇体にはコックピットの内部で見え易い個所に国際クラスフィーの銘板を取り付けなければならない。 | ||||||||||||||
| 6-3 | メインセールとスピンネッカーは規則19(3)に示す認識マークを付けなければならない。 | ||||||||||||||
| 6-4 | すべての記号、マーク及び番号は耐久力のある材料で確実に取り付けなければならない。 消えないインキで明確に描かれた記号、マークおよび番号も又承認される。 |
||||||||||||||
| 7,構造 | |||||||||||||||
| 7-1 | 艇体の構造、甲板、コクピットの配置は任意である。図面は部材寸法の例示と共に推奨する構造形状を示している。 | ||||||||||||||
| 7-2 | 甲板はデッキライン上30mmを超える部分があってはならない。波除けは甲板の一部ではない。 | ||||||||||||||
| 7-3 | 「デッキライン」とは中心線上に於けるトランサムの上縁とステム(除金物)の最高点を結ぶ仮想線でる。 | ||||||||||||||
| 7-4 | センターボードケース・スオート・肋板・敷板の構造、寸法は任意である。 | ||||||||||||||
| 7-5 | センターボードスロットは、キールに沿って測り、トランサムの後面より2,262mm(最大)と1,288mm(最小)の間にあること。ダガーボード取付の場合はキールに沿って測り、トランサム後面より1,588mmを超えてセンターボードスロットの後端があってはならない。センターボードスロットの幅は40mmを越えてはならない。 | ||||||||||||||
| 7-6 | トランサムは図面に示すように艇の最後端に取付けなければならない。 | ||||||||||||||
| 7-7 | センターライン場におけるトランサムの高さは400mm±6mmである。 | ||||||||||||||
| 7-8 | トランサムとキールの成す角度は84°±6°である。 | ||||||||||||||
| 7-9 | 艇体外面とトランサムが接する所は、その丸みが半径10mmを越えてはならない。 | ||||||||||||||
| 7-10 | 艇の長さを伸ばすような排水フラップを取付けてはならない。 | ||||||||||||||
| 7-11 | 防舷材はシャーラインにその上縁を合せて取付け、且つ、ステムの前面より50mm、トランサムの後方50mmを越えて伸ばしてはならない。防舷材の幅は固定の甲板を部分的に有する艇では外板外面より5mm以上50mm以内、甲板のない艇では5mm以上90mm以内とする。内側防舷材の幅は甲板のない艇では5mm以上35mm以内とする。防舷材の深さは35mmを越えてはならない。 | ||||||||||||||
| 7-12 | キールバンドは任意である。キールバンドを付ける場合は厚さ4mm±1mm,幅7,5mm±1mmでキールとステムの外面全長に取り付け、センターボードスロット回りでは2列に取付けなければならない。キールバンドは船殻に埋め込むとか滑らかな曲線になるようにしてはならない。 | ||||||||||||||
| 8,艇体の計測 | |||||||||||||||
| 8-1 | 艇体はオフセットテーブルによって規制される線図、即ち原寸の断面図・ステム並びにトランサムに対し確認され、又計測図に従って計測されねばならない。 | ||||||||||||||
| (Ⅰ) | 線殻の計測では正の最大偏差と不の最大偏差の合計は10mmを超えてはならない。 (線殻の計測は計測図に示すキール上の基準線とキールの距離で測る。) |
||||||||||||||
| (Ⅱ) | 各々の幅の許容誤差は±10mmである。(幅の計測は計測図による。) | ||||||||||||||
| (Ⅲ) | テンプレートによるチェックされた各断面の正の最大偏差と負の最大偏差の合計(正負の符号のみを取除く。即ち+、-を取除く。)は10mmを超えてはならない。 | ||||||||||||||
| 8-2 | 金物及び防舷材を除く艇の全長は4,030mm±10mmとする。 | ||||||||||||||
| 8-3 | 第9断面にステム用テンプレートの後端を6mm以内に位置させた時、シャーラインでのそのテンプレート上端とステムのデッキ上面との垂直距離は12mmを超えてはならない。テンプレート両端の突起の間はステムに接しているか6mm以内の間隔であること。 | ||||||||||||||
| 8-4 | 各断面のテンプレートは次のように置く。 | ||||||||||||||
| (Ⅰ) | テンプレートを両舷側材とキール上に印した点を通る仮想面に完全に合せる。 | ||||||||||||||
| (Ⅱ) | テンプレートの突起を外板面に付ける。 | ||||||||||||||
| (Ⅲ) | キール側の端を中心線に合せる。ただしキールが艇の中心にない場合には、その断面のシャーラインから等距離の個所に合せる。1断面の両舷におけるプラス、マイナスの偏差の合計が10mmを超えてはならない。防舷材はテンプレートの突起が外板に接するのを妨げてはならない。シャーラインでのテンプレートの上端から甲板の上端迄の垂直距離は12mmを超えてはならない。 | ||||||||||||||
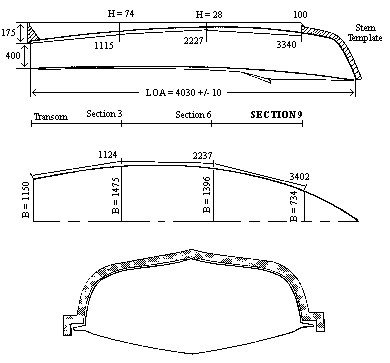 |
|||||||||||||||
| 9,浮力 | |||||||||||||||
| 9-1 | 艇は転覆又は水が一杯になった場合150㎏を乗せて略水平に浮くように充分な浮力タンクを持つか浮力袋を堅固に艇体に取付けなければならない。 1995年1月1日以降建造された艇は最小2ヶの分離したタンクを持たなければならない。 |
||||||||||||||
| 9-2 | 艇は体積が70L以上の独立の艇首用浮力袋を確実に取付けるかタンク内に入れること。容易に検査出来ること。ただし浮力袋が適用し難いときは、艇首浮力袋は独立気泡プラスチックの塊で置き換えることが出来る。 | ||||||||||||||
| 9-3 | 艇体の構造は全浮力タンク或は浮力袋の破損に際しても本来浮くようにしなければならない。 | ||||||||||||||
| 9-4 | 検査孔は水密になるよう閉鎖され、且つ、艇が浮いているときも、転覆したり水が一杯になったときでも常に外れないような取り外し可能の蓋であり、且つ、2次浮力を検査するに十分な大きさでなければならない。 | ||||||||||||||
| 9-5 | 計測員は自分で浮力区画が水密であることを確認しなければならない。 | ||||||||||||||
| 10,センターボード又はダガーボード | |||||||||||||||
| 10-1 | 構造と材料は任意である。 | ||||||||||||||
| 10-2 | センターボードを最も下ろした位置で艇より下方の部分が図面の当該部分に対し、底部と後端が(キールバンドを除く)±6mm以内にあることが確認されなければならない。キールより下方に710mmを越えて下がることのないようセンターボードに止めを付けること。 | ||||||||||||||
| 10-4 | センターボードのボルト又は切欠の位置は任意である。 | ||||||||||||||
| 10-5 | センターボード又はダガーボードは前縁を後ろ向きにしてはならない。又艇体から出たところでセンターボードの後縁が垂直より前方に回転しないようにしなければならない。 | ||||||||||||||
| 10-6 | トリムタブ(補助翼)や類似の装置は禁止される。 | ||||||||||||||
| 11,舵とチラー | |||||||||||||||
| 11-1 | 舵・チラー・チラーエキステンションの構造と材料は任意である。 | ||||||||||||||
| 11-2 | 舵板の水中部分の形状は原寸大に図面の該当部分に対し、底部と後縁が偏差6mm内であることが確認されなければならない。1996年3月1日以前に計測された舵板は2000年3月1日迄使用できる。 *注意 日本FJ協会の計測を受けている艇は、1996年以前のラダーも引き続き使用可。* |
||||||||||||||
| 11-3 | 回転式舵板でも良い。舵板の深さは舵板を一杯に下げた位置でトランサムの下端から垂直に測って600mmを超えてはならない。 | ||||||||||||||
| 12,マスト | |||||||||||||||
| 12-1 | マストは木又はアルミに限る。 | ||||||||||||||
| 12-2 | マストの位置は任意である。 | ||||||||||||||
| 12-3 | 曲りが固定したマストと回転式マストは禁止されるが、計測バンドの上下端感で40mm迄の歪みは許される。 | ||||||||||||||
| 12-5 | リギン(トラピーズワイヤーを含む)と通常の艤装品を付け、但しトラピーズシステムの取外し可能の物を除きマストの重量は、オンデッキ型で7㎏、インデッキ型で7.5㎏以上であること。 | ||||||||||||||
| 12-7 | 幅10mm以上の計測用バンドをレース中明確に認識出来る対象的な色で、以下の要領によりマストに表示すること。2と3又は2(a)と3(a)のバンドの組合わせを別個に又は併用して使用出来るが、夫々の組合わせは異なった色でなければならない。即ちブームが固定であれば1組で良い。
|
||||||||||||||
| 12-8 | スピンネッカーハリヤードの下側の延長線はマストに対して直角に張られた時に、ますと前面とNo.4バンドの下縁の上方45mm以内で交叉せねばならない。アイとか滑車でハリヤードが導かれるときは、そのどの部分もマスト前面より51mmを超えて突出してはならない。 | ||||||||||||||
| 13,ブーム | |||||||||||||||
| 13-1 | ブームは木又はアルミ合金に限る。 | ||||||||||||||
| 13-2 | トラックを含むブーム(他の部品を除く)は、直径100mmの輪を通り抜けることが出来ねばならない。 | ||||||||||||||
| 13-3 | 当初から曲ったブームは禁止される。但し、計測バンドとブーム前端の間で20mm以内の歪みは許される。 | ||||||||||||||
| 13-4 | 幅10mm以上の計測バンドをマスト後端より2、440mm以内(局部的な凹凸は除く)の所にその内縁があり、レース中明確に識別出来るように標示すること。 | ||||||||||||||
| 14,スピネッカーブーム | |||||||||||||||
| 14-1 | スピンネッカーブームをマストに軽く押し当て突出し部の接触面でその中心線に直角にしたときマストの中心線の前方でマストから1、625mmを超えて突出してはならない。 | ||||||||||||||
| 14-2 | ジブを突出すためにスピンネッカーブームを使用するときは、風上側のシュラウドに取付けても良い。 | ||||||||||||||
| 15,静索 | |||||||||||||||
| 15-1 | 静索は任意であるが、直径2mm以上のワイヤーフォアーステーを取付けること。フォアーステーは甲板面上でステムより100mm以内の点に取付けるが、防舷材の上ではいけない。 フォアーステーはジブから独立させなければならない。 |
||||||||||||||
| 15-2 | 固くて曲らないフォアーステーとランニングバックステーは禁止される。 | ||||||||||||||
| 16,動索、シート、金物 | |||||||||||||||
| 16-1 | 動索、シートや金物の材料や形状は任意である。 | ||||||||||||||
| 16-2 | ヨット競技規則64.3(a)に反してフェヤーリーダーは防舷材上に取付けても良いが、防舷材の外縁を超えて突出させてはならない。 | ||||||||||||||
| 17,禁止事項 | |||||||||||||||
| 17-1 | ジブのローラーリーフ装置。 | ||||||||||||||
| 17-2 | スピネッカーシュート。 | ||||||||||||||
| 17-3 | 電動の機器。 | ||||||||||||||
| 18,重量 | |||||||||||||||
| 18-1 | すべての固定された金物、浮力装置、保護用の塗装を含み、セール、スパー、舵、センターボード、取外し可能の金物、敷板(船体に接着された物を除く)その他の艤装品を除き、乾燥状態で艇体重量は75㎏以上なければならない。 | ||||||||||||||
| 18-2 | 重量不足(18-1)が発見された艇は補正用重錘を許容最少重量になるように取付けなければならない。補正用重錘の合計は5㎏を超えてはならない。補正用重錘は確実で、且つ、見えるような方法で艇体に取付けなければならない。補正用重錘の合計重量は証明書に記録されねばならない。 補正用重錘の変更又は取外しに伴い艇は計測委員の再計測を受け、新証明書の発行を受けなければならない。 |
||||||||||||||
| 19,セール | |||||||||||||||
| 19-1 | 全てのセールは繊布でも不繊布でも良く曲げ易く柔らかで容易に収納出来ねばならない。 本規則に規定する窓を除きセール本体は以下に規定される隅角の補強部以外はどの方向にも平らに折畳めるように制作されねばならない。セールに有効な張りを持たせるための補強材は夫々の隅角から320mm以内なら許されるが、その部分はどの方向にも折目の外形が4mmを超えないように片手で折畳めねばならない。通常のシーム又は広幅のシームより大きい2枚以上の重ね布は全て補強と見做されるが、接着剤での接着、密なステッチその他の方法で硬くならないようにしたものは許される。接着シームは補強とは見做さない。メインセールとジブセールは夫々1個の織物でない物の窓が許される。そのような窓は0、3㎡を超えてはならないし、ラフ・リーチ・フットからメインセールでは150mm、ジブでは100mmより近くてはならない。 全てのセールは完全に乾燥した状態で、且つ計測合格後各セールは特定の日付け入りスタンプを捺印し計測委員により署名されるものとする。 |
||||||||||||||
| 19-2 | セールは特記事項を除きISAF計測手引きにより製作され計測されなければならない。
|
||||||||||||||
| 19-3 | セール番号・文字・クラス記号はISRRヨット競技規則により配置されるものとする。 クラス記号は文字FJとする。FJは高さ250mm以上とする。セール番号と文字の最小寸法は下記の通りとする。
|
||||||||||||||
| 19-4 | 通常のクリングル・カニンガムホールやリーフ用アイレット以外の故意の開口は許されない。 | ||||||||||||||
| 19-5 | メインセール | ||||||||||||||
| (Ⅰ) | 3本のセールバッテンはリーチ寸即ちセールの後縁を略等分し±60mm内に取付けられること。 | ||||||||||||||
| (Ⅱ) | 1個のヘッドボードをつけても良い。ヘッドボードの幅はラフの線に直角に測って最も広い箇所で120mmを越えてはならない。 | ||||||||||||||
| (Ⅲ) | セールはどの部分でもブームバンド内縁、No.3又はNo.3(a)バンド下縁を超えて展張されてはならない。ブーム上縁の線の前方への延長線は、No.2又はNo.2(a)バンド上縁より下がってはならない。 セールのラフはセットされたとき、No.2とNo.3バンド又はNo.2(a)とNo.3(a)バンドの間になければならない。 |
||||||||||||||
| (Ⅳ) | 次の計測が行われる。
|
||||||||||||||
| (Ⅴ) | 幅の計測を回避するためリーチを凹ませてはならない。 | ||||||||||||||
| (Ⅵ) | ダブルラフとかルーズフットのメインセールは禁止する。 | ||||||||||||||
| 19-6 | ヘッドセール(ジブ) | ||||||||||||||
| (Ⅰ) | リーチは直線を超えて伸ばしてはならない。即ちリーチを膨らませてはならない。 | ||||||||||||||
| (Ⅱ) | 下記寸法を超えてはならない。
|
||||||||||||||
| (Ⅲ) | ダブルラフのヘッドセールは禁止する。 | ||||||||||||||
| 19-7 | スピンネッカー | ||||||||||||||
| (Ⅰ) | スピンネッカーは計測図に従って製作された略中心線に対象で3個の角を持つセールである。 ヘッドボード・バテン域は通常の補強(織布でも不織布でも)以外の剛性を持たせる工夫は許されない。 |
||||||||||||||
| (Ⅱ) | スピンネッカーはリーチを相互に重ねて折畳んだ中心線に沿って計測されねばならない。 | ||||||||||||||
| (Ⅲ) | 中央折目の長さはヘッドとフットの中点の間をセールの折目に沿い測った距離で4.200mmを超えてはならない。中央折目の長さはラフとフットを略水平に持ち上げ地切した状態でセールの中に巻尺を置いて測る。 | ||||||||||||||
| (Ⅳ) | クルーとタックのクリングルがセールの縁の外にあるときは計測点はセールのリーチとフットの縁を延長した交点である。 | ||||||||||||||
| (Ⅴ) | レース中は1個のみのスピンネッカーを搭載するものとする。 | ||||||||||||||
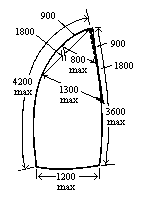 |
|||||||||||||||
| 20,艤装品 | |||||||||||||||
| レース中次の艤装品を搭載しなければならない。 | |||||||||||||||
| 20-1 | 効果的なパドル2本最少長さ950mm、最少重量300g。両方共本来パドルとして使用されるものについて計測する。 | ||||||||||||||
| 20-2 | セルフベーリングの艇を除き、あか汲み又は吸引式ベラー何れか1個。 | ||||||||||||||
| 20-3 | 長さ20.00m、直径6mm以上の合繊のもやい索1本。 | ||||||||||||||
| 20-4 | 水を入れることが出来るようなポケットが付いてなく、直ぐ使用出来る適切な個人用浮力衣。(ライフジャッケット等) | ||||||||||||||
| 20-5 | レース要項に記載されない限り、アンカーを搭載する必要はない。レース要項に記載された場合はアンカーは最少長さ20.00m、最小径6mmの合繊のロープを付け、2.3㎏を最少重量とし、アンカーと艇とを結んでおくこと。アンカーは常に使用出来る状態でなければならない。 | ||||||||||||||
| 21,トラピーズ | |||||||||||||||
| 乗員を艇外に支持する。 | |||||||||||||||
| 21-1 | トラピーズを除いて舷外貼出し又は伸縮式の舷外張り出し装置或は仕掛けと艇体・スパー・リギン又は乗員に取付けた乗出し装置の使用は禁止される。 この仕掛けはボデーベルトに取付けることにより乗員をガンネルの外に立たせることを可能にするようマストに直接又は間接に各々の側に1本迄取付けられた2本のワイヤーで構成される。 このトラピーズは1度に1人を超えて支持するように使用してはならない。 |
||||||||||||||
| 21-2 | トラピーズのボデーベルトは濡れたときそれ自身の重量で浮く、且つ3Kgを超えてはならない。 | ||||||||||||||
| 21-3 | トラピーズを使用出来る最低年齢は12歳とする。 或主催団体又は国内FJ協会が行う非国際の行事ではトラピーズの使用を禁止しても良い。 |
||||||||||||||
| 22,乗員 | |||||||||||||||
| レース中ISAFの規則によるアマチュア2名が乗艇すること。 | |||||||||||||||
| 23,クラス旗 | |||||||||||||||
| 国際信号数字旗No.1(女子はNo.2)を推奨する。 | |||||||||||||||
| 24,広告 | |||||||||||||||
| 国内協会はISRR付則による制限された広告を許される。 | |||||||||||||||